今回は5,6日目の様子を紹介します。6日目は早朝に船を降りるので5日目が実質最終日です。
5日目は午前中にボートで上陸し、午後は世界最北端の街と言われる二ーオーレスンに訪れました。
前回の記事はこちら
ツアー5日目
まず起きてデッキに向かうと大量の流氷が浮いていました。昨日より南下したはずなんですけどね。

こんなに大きな塊まで。

朝食を食べ(写真を撮るのを忘れました…)前日と同じようにボートに乗船します。
また寒中水泳するために水着を持っていきました。
午前の上陸
5日目の午前はNy-Londonと言われる以前炭鉱だった場所に向かいます。
こちら110年ほど前に作られた炭鉱で、わずか10年ほどで閉鎖し今でもその跡地が残されています。
Ny-Londonと言われるだけあって、こちらで取れた石炭の多くはイギリスに輸出されていたとそうですね。
まずはボートに乗り込みます。今回は最後のグループですね。

数分ほどして上陸。

炭鉱の跡地までは3キロほどあるそうなので、ガイドの方から地形や自然の説明を受けながら歩いていきます。

少し歩くとこのような木の棒に鉄のプレートがついたものを発見。

拡大してみたんですが120年近く前にこちらに上陸したことを記念して建てられたんですかね?

こちらの小さい池に大量に鳥が飛んでいたので何かと思って近づいてみると、大量のキョクアジサシが!

近づくと威嚇されたので、これ以上近づくのは止めておきました。

白い毛皮が落ちていたのですがガイドの方曰くこちらホッキョクグマの毛皮だそう。
本当にこのあたりにいるんですね。

ときおり動物の骨を見かけるのですが、こちらはトナカイの骨のようです。

崖を降りると炭鉱の遺跡があるようなので頑張って降ります。

崖を降りてから10分ほどしてそれらしきものが見えてきました。

こちらで石炭を運んでいたのでしょうか?

レールの跡も残っています。


Taylor & Hubbardという文字がクレーンに刻まれていたので調べてみるとイギリスの鉄道クレーンの会社のようです。

こちらは溶鉱炉だったところの跡地かな?

こちらは小屋の跡地です。このように100年以上前の建物が残っているのを考えたら感慨深いですね。


こちらの小屋は廃墟にならずにそのまま残っています。
というかここに泊まっている人がいたんですがどこから来たの!?

これで午前の上陸は終了なのですが、まだやり切っていないことが1つ。寒中水泳です。
寒中水泳
浜辺に来てみるとすでに何人か泳いでいました。自分も今から水着になって泳ぎます。

この時気温自体は10度以上ありむしろ暑いぐらいだったのですが、海水温となると話は別。
足が海水に触れたとたん今まで経験したことがないような冷たさを感じました。

冷たさを我慢し全身を浸かりピース!

このあと一目散に浜辺に上がり着替えました。泳いでいる人もいましたが当然みんなやせ我慢です。
ちなみにこちらの写真はガイドの方に撮ってもらってます。
昼食
寒中水泳後ボートで戻り昼食を食べます。
最後の昼食だったのですが寒中水泳のインパクトが強すぎてあまり覚えてない…
もうこれからの旅で魚をあまり食べられなくなると思い。サーモンと白身魚をひたすら食べていました。

午後の乗船
午後は最後の上陸ということでニーオーレスンに向かいます。
こちらは、現在民間人(と言っても各国の研究者のみですが)が住んでいる場所としては世界最北の場所になります。
以前は炭鉱として栄えていたのですが50年ほど前に事故が起きてからは閉鎖し、世界各国から研究者が集まるようになりました。
日本の極地研究所もこちらで極地の研究を行っています。
地図をよく見るとわかるのですが午前訪れた所の向かい側にあるので、あっという間に到着です。

またこちらは港があるため、ボートを使わずに普通に船から上陸しました。

街自体は北欧諸国の田舎にありそうな雰囲気です。

上陸するとこのような張り紙が。
ここの街に関するルールが書かれていますが、絶対に電子機器の通信をしてはいけないことになっています。
ここでは各国極地の研究を行っているため、関係ない電波が入ると邪魔になるんですね。

そのためどうしてもインターネットを使いたい場合は、こちらの世界最北のネットカフェ?内で有線LANがあるのでそこでのみ使用することが許されています。
自分も使ってみようと思ったのですが、そもそも自分のパソコンにはLANポートが内蔵されていないということを忘れており使えませんでした…

汽車を発見しました。こちらは炭鉱だった時に利用されていたようです。

ここの街はキョクアジサシがとにかく多いです。繁殖期だからなのかとても攻撃的でみんな襲われていました。
キョクアジサシの近くにある丸い物体が卵ですが巣は作らないのかな。割と適当ですね。


現地の方は襲われようが全く気にせず歩いていましたがこれが日常なのかも。

こちらは世界最北端の郵便局です。ここから手紙を送るとここしかない特別なスタンプを押されるそうですが本当に届くのかな?


こちらは世界最北端のホテルです。短期間滞在する人用で営業しているみたい。

こちらは世界最北端の商店です。食品や日用品が売られているこの街唯一の場所です。


物価に関しては極地であるにもかかわらずかなり安かったのが不思議。

観光客が必ず訪れると言ってもいいため、多くのお土産が並んでいました。

自分はこちらのトートバッグを購入。59ノルウェークローナ(約850円)はちょっと高い。

こちらは博物館です。入場は無料、というか無人です。

主に炭鉱だった時代に使われていた工具や生活用品等が展示されていました。

街の中心部に行くとアムンゼンの像を発見。
アムンゼンと言えば初めて南極点に到達したことで有名ですが、ここニーオーレスンから飛行船を利用して北極点まで訪れているんですよね。

前述した博物館にその飛行船に関する展示がありました。

町中をあらかた散策したため、日本の研究所を探します。
こちらは中国の研究所。玄関に立っているモニュメントがいかにも中国らしいですね。
中国人の観光客がここの前で写真を撮っていました。

こちらはイタリアの研究所。極地とは無縁な気がするのですが何を研究するのだろう。

とまあ他にも何か国か研究所があったんですが、どうしても日本の研究所が見つかりません。
帰ってきて調べてみると、以前は個別で研究所を持っていたそうですが今はどうやら別の建物の国独自ではなく各国の研究者が滞在している場所に移転しているようでした。
どうりで見つからないわけだ。
そんなこんなで2時間ほど滞在し、ニーオーレスンの街をあとにしました。
また来れたらいいね。

夕食
今回が最後の夕食ですが、夕食の前にフェアウェルパーティーを行いました。
今回のクルーズについてスタッフの方と色々話したりギターを演奏したりと大盛り上がりでした。

またパーティー中二枚の紙をスタッフからいただきました。
一枚目は北緯80度に到達したことを示す証明書。

二枚目は北極海を泳いだことに関する証明書です。海水温は7度しかなかったってそりゃ寒いわけだ。

このあと夕食をとります。夕食自体は通常と同じようなコース料理でした。
前菜がサーモンのサラダでメインがポークソテーです。

美味しかったですけど4日目のバーベキューを最終日に持ってくれば絶対盛り上がったと思うんですけどね。
ただ最終日だからなのかおかわりをいただけたのは嬉しかったかな。

デザートはアイスクリームとケーキです。

夕食後今回のクルーズで移動したが軌跡がボードに張ってありましたけど、それにしてもかなり移動したんだなあ。

ツアー6日目
6日目は8時に下船するため、これといったことはないです。
朝6時ごろ起きて荷物をまとめました。
朝食はありましたが、以前の朝食バイキングと違ってサンドイッチが配られました。

食後デッキに上がってみるとすでに出発地であるロングイエールビーンの港に到着していました。

荷物をまとめて部屋の鍵を返して下船します。スタッフの方々、6日間ありがとうございました。

下船後バスに乗り込みロングイエールビーン市内中心部に戻ります。

感想
これでクルーズは終了です。いやーこんな美しい景色を見ることができるとは…
30万円もしましたが、払う価値は十分あったと思っています。
ホッキョクグマを見ることができなかったのは残念ですけど、またスヴァールバル諸島に来いということでしょうね!
とまあ大満足のクルーズだったのですが、1つだけ残念だったことが。
2日目にロシア人が住んでいる町バレンツブルグに行けなかったということです。
どうやらロシアのウクライナ侵攻の影響でルートが変更になったようで、日本のフッティルーテンのサイトだとバレンツブルグに行くと書いてあるのですが、自分が予約した公式のサイトでは日程が変更されていました。

スヴァールバル諸島の観光サイトである、visit svalbard(https://en.visitsvalbard.com/)というサイトでもロシアに関係のある街の情報やツアーについては封鎖する措置をとっています(ツアー自体は現在も行われています。)

今のロシア情勢とは別として行けることを楽しみにしていただけに非常に残念。こっちまで巻き込むのは勘弁してほしかった…
とまあ最後は愚痴みたいになりましたが次回はスヴァールバル諸島のロングイエールビーンを少し散策した後移動する様子を紹介していこうと思いますのでお楽しみに!
次からはイギリス編です!
世界一周ブログ作るんでせっかくなんで世界一周ブログ村のランキングに参加しようと思います。
応援としてクリックしていただけると嬉しいです!
↓↓↓↓↓
にほんブログ村
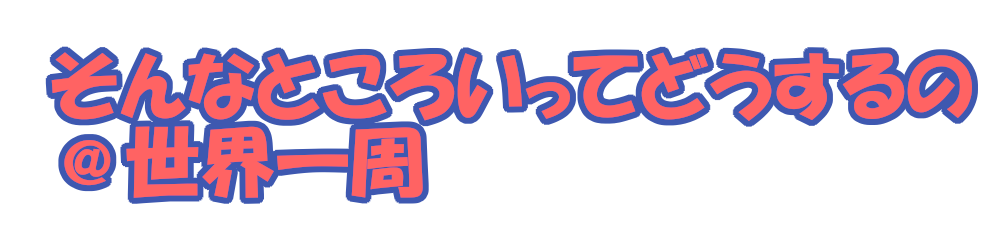




コメント